長谷川集平/文 村上康成/絵 '87年 BL出版 B5変形 ¥1,400
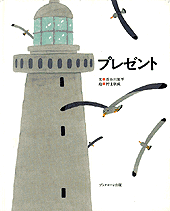
クリスマスの朝、おじいさんは灯台守の子どもに聖母子像の絵を届けに行く。
雪の降る海を、ヨットと並んで静かに進むかいじゅう。
照らしてくれ、遠くまで。君だけがたよりなんだ──
奥深い3つの物語を締めくくる決定的な作品。
ボローニア国際児童図書展グラフィック賞受賞
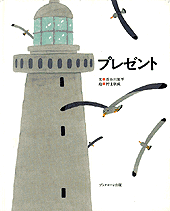
クリスマスの朝、おじいさんは灯台守の子どもに聖母子像の絵を届けに行く。
雪の降る海を、ヨットと並んで静かに進むかいじゅう。
照らしてくれ、遠くまで。君だけがたよりなんだ──
奥深い3つの物語を締めくくる決定的な作品。
ボローニア国際児童図書展グラフィック賞受賞
「三部作をめぐって--長谷川集平・村上康成インタビュー」
(「MOE」'88.4月発行号より抜粋)
(前略)
長谷川 できてから出版されるまで10年かかって、かえって良かったと思います。絵とか文章っていうのは、ものごとを理解しないと描けないから。例えばヨットの絵は、ヨットを知っている人が描くのと知らない人が形だけ見て描くのとでは全く違う。同じ意味で、海もそうだし、"かいじゅう"もそう、人間もそうだしね。僕たちもこの10年間いろんな意味で成長してきましたから、20歳前後の若者だった10年前より今の方が描けるんじゃないかな。ひらめき自体は間違ってなかったんだけど、表現しきれる力がまだたりなかった…。
(中略)
長谷川 その10年の間に、三部作にふくらんでいきました。ところでこの話、ファンタジーではなくてリアリズムなんですよ。実話。僕は"かいじゅう"を見たことがあるんです。
(中略)
村上 絵も、現実に存在する生き物として描いています。きっと"かいじゅう"に対する集平の思惑っていうのはあると思うし、僕の思惑っていうのもあるんだけど、それについての具体的な話し合いっていうのは何もなかった。そこは10年間のつき合い……(笑)。
長谷川 2人の重なっている部分、一致している部分が"かいじゅう"だということ。2人とも"かいじゅう"を見ているからこそ、この三部作か生まれたんです。"かいじゅう"に何を見るかは僕ら2人ですでに違っているし、読む人一人一人が自分なりに考えてくださったらいいと思います。決まった答えはありません。答えがあるとすれば"かいじゅう"です。『プレゼント』は、なぜ僕らが子どもの本をかいているか、という一つの答えとして提示したつもりです。この本をかいた最大の理由は、僕は、ずっと見失っていた子どもの本を描く理由(それがしばらく絵本をかけなかったわけの一つなんだけど)をようやくつかみかけたっていうこと。康成にとっては、具体的に自分の子どもができたっていうこと。僕らが、自分のであれ他人のであれ子どもに対してどういうふうに関わっていけるかということを、僕らなりに一つのストーリーで語ろうとすれば、こういう本になるだろうな、ということなんです。中に出てくる母子像というモチーフには、普遍的な、誰もがひかれるものがあると思うんです。人間のあり方の原型として、誰しもの中の深いところに根ざしているのではないか。登場するおじいさんのように、ひとつの愛の形を誰かにプレゼントしていく、渡していく関係っていうのは、子どもの本の中に本質的にあると思うんです。男の子が闇を照らしている光、というのは実感です。
村上 まさにそうですね。子どもは光です。なんと明るいことよ(笑)。
長谷川 人間って自惚れが強いから、いつもは自分で光を放っていると思ってる。でも、ある時ふっと、実は自分が誰かに照らされている、月みたいなもので誰かのまわりを回ったり、導いてもらったりしている──と感じることがあると思うんです。そんなときに読んでもらえたら、スッと受け取めてもらえるんじゃないかな。
村上 最近、本を読むと、すぐ答えというか結果を見つけたがる傾向があるでしょう。「これは何の本だ」という。そういう人に一番読んでほしい気がします。この本は、どういう本だと言ってしまうこと自体が違う絵本。その時その時で何か拾ってくれればいいと思います。
長谷川 それは、表現にとって一番理想的な形だと思うんです。自然のものには、例えば葉っぱ一枚にも、宇宙を語れるようないろんな秘密が隠されているわけでしょう。僕らは、そういうものを目指したいんです。だから、いろんな解釈とかくみとり方のできるものをもし僕らが作れたとすれば、やったな! と思います。